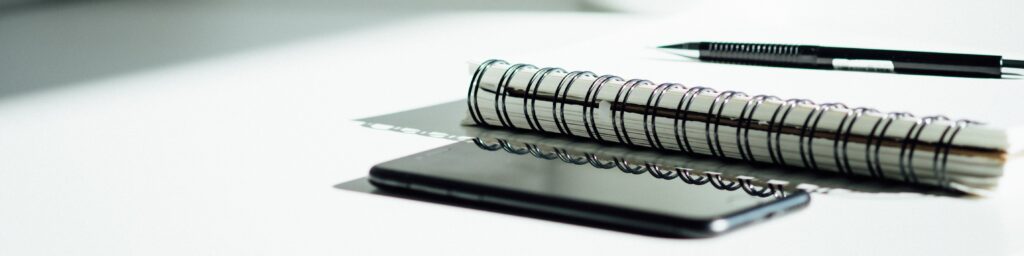法人税法の損金算入について求められる債務の確定の意義について、債務の確定があるといえるためには、3つの要件がある。1つ目は、債務が成立していることであり、契約を成立しているこという。2つ目は、当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していることであり、契約に基づいて、注文した物品の納品やサービス等の提供を実際に受けて完了していることが必要で、取引先からもらった納品書等で、納品日やサービス提供日を確認するのである。3つ目は、その金額を合理的に算定できるものであることであり、納品された商品やサービスの代金が、期末までに確定して、分かっているということである。
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額の範囲は、3つあり、1つ目は、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額である。2つ目は、1つ目の原価の額に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額であり、償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除くものとし、3つ目は、当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものである。
原価の額は、売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる額である。売上原価は、当該事業年度における売上高に直接対応する費用であり、建設業では売上高の代わりに完成工事高ということから、これに対応する費用を完成工事原価という。そして、棚卸資産の評価では、ある事業年度の収益に係る売上原価を算定するには、当該事業年度においてどれだけの棚卸資産が売れたかを決める必要で、そのためには、期首にどれだけ在庫があり、期末にどれだけ在庫が残っているかがわかればよい。そこで、当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の価額を評価し、棚卸資産の評価方法は政令に委任されている法人税法施行令28条1項で原価法と低価法があり、それ以外の評価方法については、所轄税務署長の承認が必要で、取得価額の範囲は、直接要した費用も含まれる。収益と直接的・個別的に対応される結果、恣意性の入り込む余地がほとんどなく、納税者による所得操作の可能性が少ないため、債務が確定していなくても、適正な見積額を損金算入できるのである。
費用の額は、販売費、一般管理費その他の費用の額、会社の販売および一般管理業務に関して発生したすべての費用であり、公正妥当な会計処理の基準に従い、原則として損金に算入する。損金算入のタイミングを規律するものや、損金算入を制限するものなどがあり、租税特別措置法にも、交際費に関する規定のように、損金算入を制限する規定がある。法人税法22条3項2号括弧書きは償却費以外の費用と規定しているため、償却費については債務の確定をまたず損金の算入がみとめられる。法人税法は、減価償却資産と繰延資産については、償却費の計算及び償却の方法を定める。いずれも、複数の事業年度にわたって生ずる収益に対応させて、費用控除のタイミングを分割し複数事業年度に割り振っている。企業の事務負担に配慮し、減価償却制度を簡素合理化する趣旨で、少額減価償却資産について、即時損金算入がみとめられている。すなわち、内国法人がその事業の用に供した減価償却資産で、使用可能期間が1年未満であるもの、または、取得価格が10万円未満であるものを有する場合において、損金経理した金額を損金に算入する。
損失の額は、当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものと定め、損失とは、収益稼得に貢献しない資産の減少のことである。損失は、費用とは異なり、費用は収益の稼得に必要な支出だからである。法人税法22条3項3号と密接に関連するのが、資産の評価損に関する33条の規定であり、法人が資産の評価替えをしてその帳簿価額を減額しても、原則として、その事業年度の所得の金額の計算上損金には算入できない。例外として、災害による著しい損傷により資産の時価が帳簿価額を下回ることになった場合や、会社更生法による更生計画認可の決定による場合、民事再生法による再生計画認可の決定による場合などに、損金算入がみとめられる。
参考:租税法入門(第2版)